お米を精米した時に出る粉が「米ぬか」です。
土作りの段階で肥料を与えることで肥料の効果が長続きしますし、何より安価で手に入りやすいのも魅力です。
米ぬかにはどんな効果があるの?米ぬか肥料の作り方は?土に混ぜる時の注意点とは?肥料として使うメリット・デメリットは?
ポイントは発酵させること。発酵が不十分だと失敗してしまう原因になります。
スポンサーリンク
関連のおすすめ記事
-

男は身長が160台でも、包容力と着こなし次第で恋人はできます
男は外見ではなく中身だという女性もいますが、どうしても身長160台だと自信がないと感じる男性も多いで...
-

夕飯のメニューが決まらないときのお助けメニューや対策を紹介!
毎日夕飯のメニューは何にしようか困ってはいませんか?お肉・魚・野菜・などバランスよく摂りたい...
-
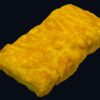
お弁当の卵焼きに一工夫!人気のアレンジレシピをご紹介します!
お弁当のおかずとして卵焼きは欠かせませんが、どうしても味や見た目がワンパターンになってしまいますよね...
-

バラの花びら活用方法!押し花・ドライフラワー・ポプリの作り方
あなたの誕生日に大切な人からたくさんのバラの花をもらったら、そのバラをいつまでも残しておきたいと思う...
-

包丁の研ぎ石は100均の物でも切れ味復活。特徴と使い方を紹介
毎日使う包丁は切れ味がどんどん落ちていきます。食材が上手く切れないと料理をする時にストレスに感じるこ...
-

うさぎの寿命で最期が近づいた時に飼い主としてしあげられること
今までずっと家族の一員として可愛がってきたうさぎも、寿命で最期の時を迎える時が必ずきます。別れは...
スポンサーリンク
米ぬかにはどんな効果があるの?米ぬか肥料の作り方は?
米ぬかを肥料に使うと、どんな効果があるのでしょうか?
まず、良い肥料には「窒素」と「リン酸」と「カリウム」が欠かせません。
米ぬかを肥料に使うと、「窒素」と「リン酸」と「カリウム」のバランスが良いので、ナチュラル肥料の材料としてオススメです。
効果としては、「植物の成長と生育」を手助けし、また、肥料成分が高すぎないので、多くまいたとしても、土や植物への影響は少ないです。
しかし、そのままで使用するには、まだ不十分ですから、「米ぬか肥料」にして、良い肥料を作りましょう。
その米ぬか肥料の作り方は、以下の手順になります。
- ダンボールや、プランターなど、少し隙間があって、空気の出入りが出来る容器を準備します。
※衣装ケースのように、密閉度の高い箱を使いたい場合は、上のほうにドリルなどでいくつか穴を開けましょう。
また、ダンボールを使用する場合は、箱の下に風を通すために、四隅に足を付けましょう。 - 箱に腐葉土などの黒土や、ピートモスなどを入れ、一緒に混ぜます。
- 生ゴミを追加し、生ゴミと同じ分だけ米ぬかを入れ、よく混ぜます。
- フタをして、毎日混ぜ、中身をなじませます。
- 生ゴミが出たら、またその分だけ米ぬかを混ぜます。
- 箱が一杯になったら、追加するのはやめて、毎日混ぜるだけの作業を10日ほど行います。
- 発酵のため、1ヶ月ほど放置させれば出来上がりです。
肥料効果抜群の米ぬか、土に混ぜる時の注意点とは?
肥料効果抜群の米ぬかですが、土に混ぜる時の注意点には何があるのでしょうか?
まず、ひとつめは、「生の米ぬかを使わない」ことです。
生の米ぬかを使ってしまうと、微生物によって急速な分解が行われ、土の中の窒素が無くなってしまいます。
窒素は植物の生育に欠かせないものですから、土に良さそうと思って生の米ぬかを撒くと、逆に生育の妨げになってしまいます。
次に注意したい点は、「暑い時期に発酵させると、虫の温床になる」ことです。
米ぬかや、それと一緒に入れる生ゴミは、発酵させれば、植物にとってご馳走ですが、それと同時に虫たちにとっても、住み心地の良い場所になります。
発酵は、夏と秋の暑い時期ではなく、冬の寒い時期に行うと良いでしょう。
米ぬか肥料の効果、肥料として使うメリット・デメリットは?
米ぬか肥料は、自然なものですから、メリットしかないと思われますが、デメリットだってもちろんあります。
そんな、米ぬか肥料のメリットとデメリットをご紹介します。
まず、メリットですが、
- 有機物なので、畑にいる菌たちやミミズが増え、土壌が豊かになる。
- 化学肥料より肥料成分が少ないので、多少まき過ぎても土や植物に影響が少ない。
- 値段が安い。また、地域によっては、無料で手に入るところもある。
などのように、有機農法にこだわる人や、少ない費用で肥料を作りたい人にはおすすめです。
次に、デメリットですが、
- 発酵させるまでに、手間と時間がかかる。
- 米ぬかや生ゴミを材料としている為、虫が湧き、それを狙ったネズミも来てしまう。
- 化学肥料に比べて、効き目が出るのが遅い。
- ニオイが出るし、長期間置きっぱなしにすると、腐ってしまう。
など、自然なものゆえ、腐ったり、虫が湧いてきてしまう事がありますので、虫対策をするなど、少し手間のかかるものになります。
米ぬか発酵肥料、比較的早くできる好気性発酵の作り方とは?
好気性発酵とは、空気に出来るだけ触れさせ、空気のある状態を好む微生物によって肥料の材料を発酵させるものです。
具体的な作り方は、どのようなものなのでしょうか?
- まず、材料は、米ぬか以外は、腐葉土(黒土)、生ゴミ、もみがら、あぶらかす、鶏糞などをつかいます。米ぬかと腐葉土以外は、2~3種類ほどを入れると良いでしょう。
- これらをプランターなどの中で、よく混ぜます。
水分は、うっすら湿っているくらいで大丈夫です。 - 混ぜ終えたら、物置の中など、雨の当たらないところに置きます。
この時、新聞をかぶせるなどして、密閉しないようにしましょう。 - 発酵が進むと、中の温度は50度ほどまで上昇します。
時々混ぜて、空気を含ませましょう。
発酵臭が気になるときは、マスクをして作業しましょう。 - 発酵が落ち着いたら、温度も上がらなくなり、匂いも少なくなります。
そうしたら、中身を新聞紙やシートなどに広げ、天日干しします。
乾いたら、ホームセンターで売られている、肥料や作物を入れる用の紙袋に入れましょう。
米ぬか肥料作りに失敗してしまう原因と対処法
米ぬか肥料作りに失敗してしまう原因と対処法についても、学んでいきましょう。
まず、肥料として米ぬかを使うのなら、発酵させてから使いましょう。
そのまま撒いてしまうと、虫が湧く原因になってしまいます。
肥料の使い方として、「土に混ぜる方法」と「土の上からかける方法」がありますが、米ぬか肥料は「土に混ぜる方法」を選んでください。
また、使用する量も、自然で土に影響が少ないからといって、いきなり土に大量に混ぜるのもやめましょう。
これも、虫を招いてしまいます。
これらの事に気をつければ、米ぬかを肥料として使うのに役立ちます。
米ぬか肥料を作るのには、手間と時間はかかりますが、費用が安く抑えられて、自然な方法で作物を作る事が出来ますので、ナチュラル思考の方にはおすすめの肥料です。





















