夫婦として生活していても、何かの原因があって夫婦関係が上手くいかず、離婚を考えることもあるでしょう。喧嘩が絶えない、DV、浮気など、結婚生活を続けて行けないと感じたら、離婚という選択肢もでてきます。
離婚を考えた時、子供がいない夫婦よりも子供がいる夫婦の方が慎重になりますよね。親の離婚は子供にどんな影響を与えるのでしょうか。
そこで今回は、親の離婚が子供に与える影響についてお伝えします。
スポンサーリンク
関連のおすすめ記事
-
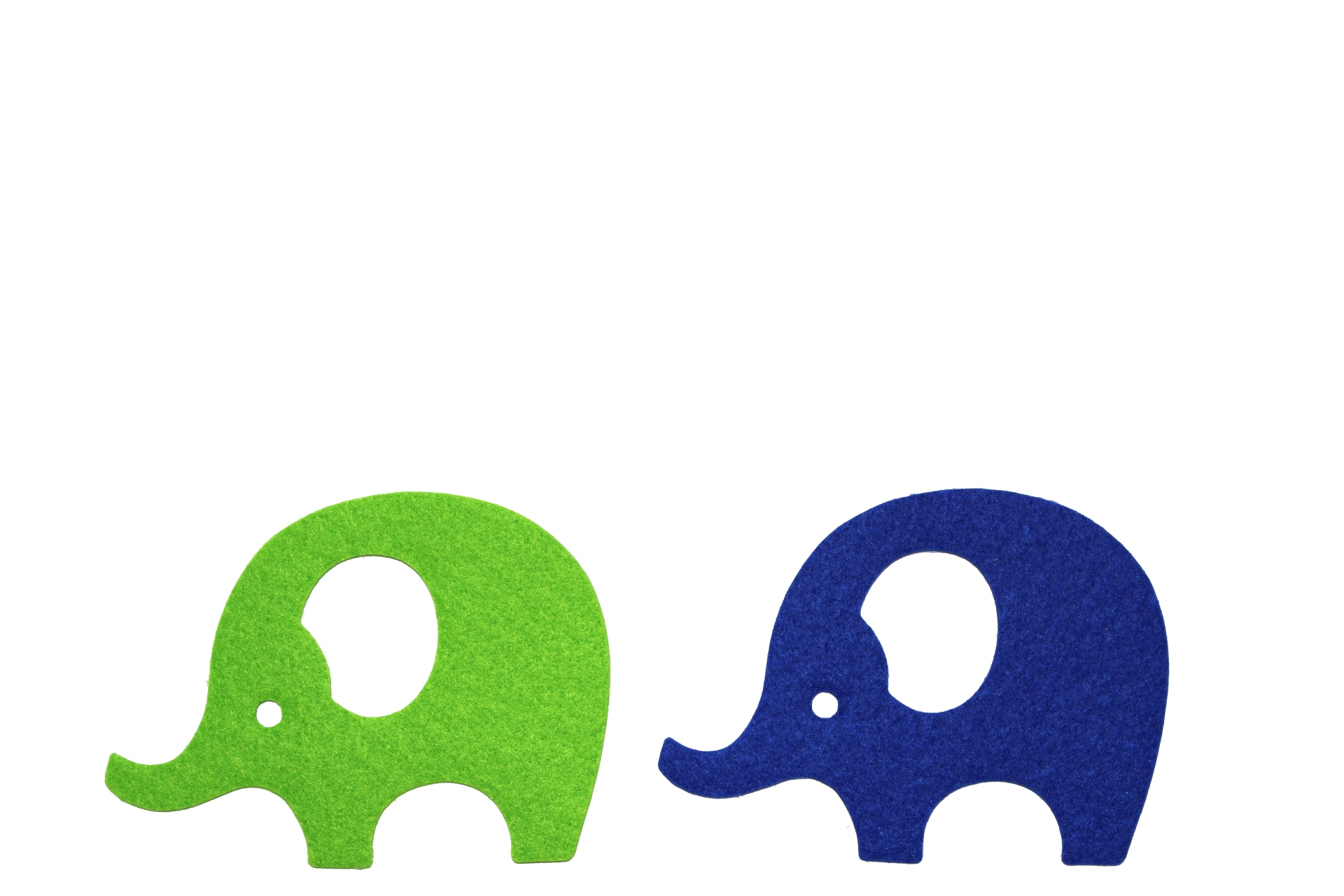
フェルトでワッペンを手作りする方法と手作りする場合のポイント
子供のバッグにフェルトで手作りしたワッペンをつけて、オリジナリティ溢れる可愛いバッグにしてみませんか...
-

舞茸の天ぷらがべちゃべちゃに…この方法ならべちゃっとしない!
舞茸の天ぷらって、無性に食べたくなる時があるのは、私だけではないはずです!素材は舞茸のみ。...
スポンサーリンク
親の離婚が子供に与える影響
離婚を決めるときは、前向きな未来のために決意を固めると思います。
しかし、親も予想外な影響が子供に表れることもあるのです。
親が離婚すると子供の成績や社会的地位の低下が見られる
離婚というのは、親にとって子供のために決断する場合もあります。
しかし、子供が幼ければ幼いほど、親に見離されるような不安を感じるようです。
その不安感から、成績や社会的地位が低くなるような傾向があるようです。
親の離婚で物や人への愛着が低下する
子供は日々の生活の中で、両親や兄弟、ペットといった家族関係に強い愛着を感じて生活しています。
両親が離婚をして、自分の感じてきた愛着に変化が起こると、愛情という感情に疑問を抱き始めます。
そして苦しみも生まれることがあります。
精神的なトラブルが多くなる
両親が離婚して間もない環境の子供は、精神的に混乱することが多いということがわかっています。
ストレスを感じやすくなり、不安を抱きやすくなります。
時間とともに落ち着いてきますが、中には長期に渡ってこのような感覚に陥っていく子供もいるようです。
親の離婚が自分の存在が影響しているのではないかと考える子供も
子供は親の影響を強く受けます。
小さなうちは特に、親が自分の世界の多くを占めます。
そんな両親の離婚というのは、やはり子供にも影響を与え、子供なりにいろいろ考えるようになります。
子供自身が「自分のせいで離婚してしまった」と思うこともあります。
決してそんなことがなくても、両親がそのように思わせてしまう環境を作っていることもあるのです。
離婚を決断するともなれば、家庭内の雰囲気は決して明るいものではないでしょう。
顔を合わせるたびに、喧嘩になることもあるでしょう。
子供に喧嘩している場面を見せてしまったり、相手への不満を子供に話したりしていませんか。
子供は自分自身にも責任を感じるのです。
もし、夫婦関係のストレスから子供との時間を大切に出来ていなかったり、八つ当たりのような対応をしていたら、さらに強く責任を感じます。
このような気持ちを引きずらないためにも、子供には責任はないことを両親の言葉で伝えてあげましょう。
親の離婚が自分の人生にどんな影響を与えるのか心配する子供は多い
子供は親が離婚した場合、自分の今後のことが心配になります。
一人ぼっちになってしまったらどうしよう…。
住む場所は変わるのかな?
もう離れてしまう親には会えないのかな?
いろいろなことで頭がいっぱいになります。
何もわからずに、不安を感じることはとても辛いことです。
不安に感じていることを取り除き、今後も大丈夫だと安心させてあげて下さい。
子供に愛情をたくさん伝えること
両親が離れ離れになってしまったら、自分は誰と一緒に暮らすことになるのだろうと不安と孤独を感じます。
一人ではなくても、一人ぼっちになったような感覚になります。
このような不安や孤独を取り除いてあげられるのは、親が誠意を持って子供に愛情を持っていること、離婚してもその愛情は変わらないことを伝えましょう。
抱きしめてあげたり、子供との時間をたくさん作ることで、少しずつ安心感に変わっていきます。
絶対に子供を一人にさせない
離婚をしても、あなたを一人にさせないということも伝えてあげましょう。
ずっと一緒にいるということを伝えてあげると、不安を解消してあげられるでしょう。
子供は今まで通りに近い生活を望んでいます。
離婚しても、今までと変わらず一緒だということを伝えてあげて下さい。
親の離婚は子供に連鎖する?
両親の離婚を経験している子供も大人になり、自分自身も結婚するときが来るでしょう。
統計的に見ると、両親の離婚を経験した子供が将来離婚したり、未婚の親になる確率は、離婚を経験していない子供に比べると約3倍多くなると言われています。
考えられる要因としては、自分自身が過ごしてきた家庭環境や行動が関係あるのではないかとされています。
例えば、両親が離婚直前に相手の悪口を子供に言っていたとします。
このような環境で育つと、それが当たり前のような感覚になり、結婚後も同じ行動をしてしまいがちです。
両親の仲が良く、お互いに尊重し合っている両親を見て育つと、夫婦とは尊重しあうものだと考え自然と相手のことを思いやることが出来たりするのです。
また、離婚して金銭的に裕福ではなく、進学を断念する人もいるでしょう。
そのような事情で収入の安定が低い仕事に就き、結婚後の自分の生活も苦しくなり、離婚に発展するケースも少なくはないようです。
親の離婚が子供に与える影響は大きい
親の離婚が子供に与える影響と一言で言っても、子供の年齢によっても影響は違ってくるようです。
0~2歳の乳児期の子供に親の離婚がどう影響するのか
親の記憶もないくらい小さいうちなら、子供に与える影響は少ないと早くに離婚を決断するケースもあると思います。
もちろん理由によっては、離婚した方が子供もためになるケースもあります。
これから成長していく子供のために、注意しておきたいことは、乳児期の子供は母親の愛情をたくさん必要としています。
愛情を十分に感じることが出来ないと、心が不安定になってしまいます。
もちろん仕事など、仕方ない事情はありますが出来るだけ子供との時間作りもしてあげましょう。
3~6歳の未就学時期に親が離婚すると?
未就学時期の子供は、幼稚園や保育園にも通いだし社会性を身に付けていきます。
そして、自分と他人をはっきりと区別するようになります。
友達は両親揃っているのに、なぜ自分はそうでないのかということに疑問を感じ始めます。
嘘をついて誤魔化すことは、結果として子供を傷つけることにもなりかねないので、きちんと話をしてあげることが大切です。
7~18歳の学生時期に親が離婚する場合は見守ることが大切
この時期の子供は、ある程度の環境や内容を把握します。
両親の離婚に傷付くこともあれば、そうでもない場合もあります。
傷付いてしまう子供は、この先のいろいろな変化を親が気付いてあげたり支える存在になってあげる必要があります。
そうでない子供でも、少なからず葛藤した気持ちは抱えています。
しかし、親以外の友達などの存在でも支えとして感じることが出来ます。
適度な距離を保ちつつ、見守ってあげることが大切ですね。

























