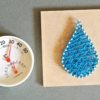7歳の女の子のお子さんがいるママたちの中には、七五三の着物を自分で着付けてあげようと考えている人もいるのではないでしょうか。ですが、着付け方がわからないと、うまく着付けることができないものです。
ここでは、7歳の女の子の七五三の着物を着付ける方法のついてお伝えします。
着付けに必要なものや注意点・ポイントをチェックして、可愛く着付けをしてあげましょう。
7歳の女の子の七五三は3歳の着付けに比べると少し手間がかかります。ですが、大切なお子さんのためにも、愛情をもって素敵に着付けをしてあげましょう。
七五三の良い思い出を作ってください。
スポンサーリンク
関連のおすすめ記事
-

魚焼きグリルの掃除方法!内部のベタベタ汚れを綺麗にする掃除法
お魚を焼いた後の魚焼きグリルの内部には、ベタベタ汚れや頑固な焦げ付き汚れが残っていますよね。油断して...
-

お誕生日に作りたい料理【4歳児におすすめのパーティーレシピ】
お子様のお誕生日には、どんな料理を作ろうか悩んでいるママも多いと思います。いつもとは違った特別感...
-

金魚のヒーターの電気代を確認。ヒーターの選び方と電気代節約術
金魚の飼育には水槽やエサから始まり、フィルターやポンプなどが必要です。また寒い時期や地域によって...
-

家で趣味を女性一人でも楽しむ!インドア派向けのオススメを紹介
家でできる趣味なら女性一人でも簡単に楽しむことができます。家に居るとついダラダラしてしまうという人も...
-

唐辛子の収穫方法と収穫時期は?おすすめの調理法と病気害虫対策
家庭菜園で唐辛子を育てている人の中には、収穫方法や収穫時期がわからない人もいますよね。唐辛子を収穫す...
-

単身赴任の夫の食事が心配なら、持たせるおかずのオススメとコツ
夫が単身赴任だと、食事のことが心配ですね。仕事忙しいとご飯を作る時間や余裕もなく、カップ麺や...
-

夜ご飯は簡単&時短の丼ものにしよう!冷蔵庫にある野菜を活用!
仕事をしながら子育てしていると、毎日の夜ご飯の献立を考えるのも面倒でなんとか簡単なもので済ませたい、...
-

小姑と同居することに!【必見】出戻りの小姑と同居する時のコツ
夫の実家で義両親と同居生活をしているところに小姑が出戻りをして同居することになったら、ただでさえ大変...
-

セキセイインコの性別はいつわかる?性別がわかる時期と見分け方
セキセイインコの性別がいつわかるのか、どこをみて判断できるのかは気になるところ。でもセキセイインコの...
スポンサーリンク
7歳の七五三の着物の着付け方・必要なもの
7歳の七五三の時に着る「四つ身」という着物は、大人の着物と同じつくりで作られ、子供のサイズに合わせて小さくつくられた着物をいいます。
7歳になると楽しんで着られることが多くなるので、着付けに時間がかかる大人と同じ作りのものが着られるようになります。
準備するものは、四つ身の着物、長じゅばん、肌じゅばん、裾除け、帯、タオルを2~3枚、足袋、紐を5本、伊達締めを2本、帯板を2枚、帯枕、三重紐、帯揚げ、しごき、帯締め、箱せこ、扇子、バッグ、草履、髪飾りです。
作り帯を使う場合は、帯枕、三重紐は必要なく、帯板を1枚だけ用意してください。
全体のコーディネートがされているのでとても可愛く、まとまり感があります。
我が家も娘の七五三にはセットになっていたものを購入しましたが、用意するものが肌着だけだったのでとても便利でした。
新しく購入した着物の場合、肩上げが必要になります。
子供の体の大きさに合わせて身丈を調整するもので、子供の健やかな成長を願う意味もあります。
お直し屋さんに頼むこともできますが、難しい作業ではないので成長を願って自分でやってみましょう。
着物の着付け方のポイントと注意点
普段着物を着る機会はあまりないので、着付けに慣れていないことが多いのではないでしょうか。
着付けに時間がかかってしまうと、子供にとっては苦しい時間が続いてしまい、おめでたい行事の七五三が辛い思い出として記憶に残ってしまうかもしれません。
七五三は楽しい思い出であってほしいので、事前に着物の着付けの練習を行い、当日に備えましょう。
お化粧や髪のセットは、着付けをする前に済ませるようにしましょう。
大人でも着物でトイレに行くのは大変ですから、子供にとってはもっと大変なので、着付けの前に済ませておきましょう。
7歳の七五三の着付け方の手順・足袋を履かせて~伊達締めまでの手順
初めて本格的な着物を着る経験なので、ひもをきつく結んでしまうと苦しい思い出になってしまいます。
結び目が痛く感じることもあるので、結び方にも気を配りながら可愛らしく着付けてあげましょう。
まず初めに裾除け、肌じゅばんを着せ、足袋を履かせます。
仕上がりがきれいになるように、腰のくぼみにタオルを巻き、ひもで結んで留めます。
子供の体形にあわせてタオルの枚数を調整し、細身の子供は多めに巻くなどしましょう。
次に長じゅばんの衿を首に沿わせるように着せて、腰ひもを後ろで二重でねじり結びにします。
背縫いが中心にくるように注意しましょう。
向かって左側を下前、上前の順で合わせ、前衿をのどのくぼみが隠れるように合わせます。
後ろ衿を指が1~2本入る程度に抜きます。
着物を着せて、長じゅばんの袖を着物の袖に通します。
衿を前で合わせ、着物と長じゅばんの背縫いが合うように洗濯ばさみなどで留めておきましょう。
上前で着丈と身幅を決め、おはしょりを返します。
腰ひもを締めて、おはしょりを整えます。
半衿を1.5~2センチくらい出して合わせます。
おはしょりは都度整え直しましょう。
胸紐を締め、伊達締めを締めます。
胸紐はゴムベルトがあれば便利ですよ。
ゆるくしすぎると着崩れしやすいので、適度な締め加減にしましょう。
七五三の着物の着付け方・帯の結び方
七五三の着物の帯を着付けるときは子供の後ろに座り、帯を二つ折りにして手の長さを取り、子供の左肩に掛けます。
帯の先を子供に掴んでいてもらうとズレにくくなります。
また、帯は折りたたんで開く側を上にします。
帯をひと巻きし、ぎゅっと締めてからもう一巻きします。
ふた巻き目の時に、折った帯の間に帯板を挟みます。
もう一度帯をぎゅっと締めます。
帯を斜め上に折って、初めに肩に取っておいた側とひと結びし、脇の部分を整えます。
右側に垂れた帯は広げ、左側にきた帯はひだを付け洗濯ばさみどで留め、子供の右肩にかけます。
帯の結び目のすぐ上で仮紐で結んで留めます。
仮紐はふた巻きします。
垂れた帯を肩幅より少し広めの幅に、内側に返すように折りたたみます。
降りたたんだ帯の内側にきた部分を下に引き出すように10センチほどずらし、真ん中をくしゅくしゅっとまとめてリボンのような形に整えます。
先に結んだ仮紐のひと巻き目に通して留め、反対側からもふた巻き目の仮紐に通して留め、帯の形を整えます。
作り帯の場合は、帯を巻き、紐を前側で結んで帯の中に入れて隠し、作り帯をさして紐を結び、帯の中に入れて隠します。
帯揚げを巻き、帯締めを締めます。
しごきを折り目が内側に来るように7~8センチ幅に折りたたんで帯の下に巻き、後ろで大きな蝶結びにします。
この時、結び目が帯の真ん中より左に来るように位置を調整しましょう。
最後に箱せこを胸元に挟み、帯締めに扇子を挟んで飾ります。
作り帯の場合は、これで完成です。
7歳の七五三の着物の着付け・帯枕~完成までの手順
リボンのように整えた帯の下に、帯枕を入れて結んで留めます。
結んだひもは帯の中に入れて隠します。
帯揚げを後ろから巻き付け前で結びます。
ひだを付けて右肩にかけておいた帯を下ろし、丸く織り込んで帯締めを締めて留めます。
帯揚げの結び目を一度ほどき、整えて締め直します。
下前側は帯の間に挟み、上前側は斜め上にして上前に挟みこみます。
しごきを折り目が内側に来るように7~8センチ幅に折りたたんで帯の下に巻き、後ろで大きな蝶結びにします。
この時、結び目が帯の真ん中より左に来るように位置を調整しましょう。
帯の形を再度整え、箱せこを胸元に挟み、帯締めに扇子を挟んで飾ります。
全体のバランスをみて歪みや曲がりがないか確認し、整えて完成です。